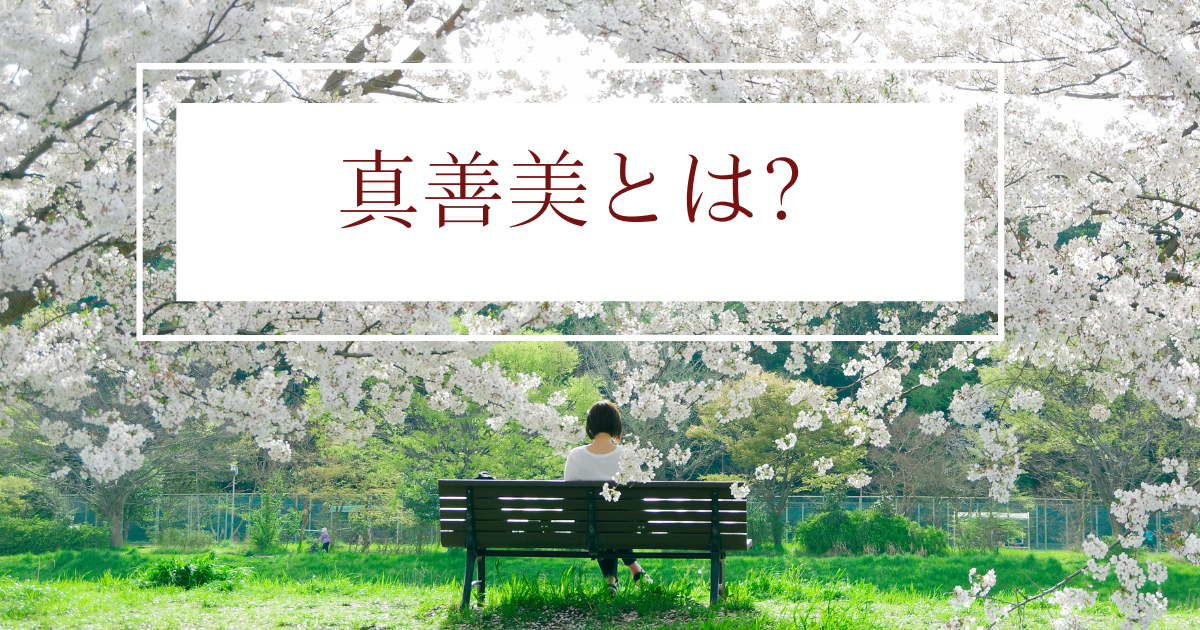「真善美って何?」「何のために必要なの?」「そもそも本当に存在するの?」
哲学や文学あるいは政治学や社会学を勉強している時に、この言葉をふと目にした学生さん。もしくは仕事で「これからのビジネスには真善美の価値観が重要だ」と言われたことのあるサラリーマンの方。そうじゃなくても、ボランティアとかの社会貢献に熱心か、または興味を持っている方は、この概念を知った時に一度はこう思ったんじゃないでしょうか。
上記にあたる方でなくても「どうしたらもっと人、社会、国、世界、が良くなるか」を少しでも考えている方は、この記事は必見です。
この記事を読めば、人間の理想の姿を表す「真善美」の「定義と概念」、「なぜこれからそれが必要なのか」、それが「存在するための前提」と、その「個人的・社会的・政治的意味」、さらには「良い生き方って何? そんなのあるの?」「真善美を実現するためにまず心がけるべきことは?」ということが一通り分かります。
知識が足りない部分に関しては、これからこのブログを書いて皆様と知識や知恵を共有していく中で、私自身しっかり学んで勉強していこうと思っています。なので、これからも空いた時間にお立ち寄りいただけると嬉しいです。
それでは一緒に「真善美」の世界へ行きましょう!
①真善美とは?
1その定義と概念
真善美とは人間の普遍的な理想のあり方や価値を示す概念のこと。
真=知性における最高価値 善=道徳や意志における最高価値 美=感性における最高価値
「清く、正しく、美しく」ってやつですね。
古代ギリシャの哲学者プラトンの「イデア論」がもとになっています。プラトンの「イデア論」に関しては、これから先で詳しく説明します。
2なぜ、これからの時代に必要か?
真善美は、内面の良さやものの本質を表す概念のため、「正解」がなく「倫理・道徳」が重要になるこれからの時代に人々が何かを評価するときの指標になるから。
高度経済成長期の合言葉でもあった「友情・努力・勝利」。この分かりやすく画一的な価値観の中で、皆が一つの目標を目指す時代は終わりました。それと同時に、力の強さや数の多さのような今まで信じていた目に見える指標が、通じにくくなってきたのです。「何が正解か分からない」もしくは「正解がたくさんある」。そのような今日の多様性の社会をうまく機能させていくために重要な価値観が「真善美」なのです。
「真善美」というのは、そのものの内面の質を問う価値観なのです
言い換えると、多少強引ではあっても前の時代は「勝てさえすればよかった」のです。力でも数でも不正なやり方でも。不正行為もしくはパワハラ・セクハラなどの問題が指摘されることは、一昔前にもあるにはありました。ですが、当然その数や追及のされ方も今の時代の比ではなかったのです。
「真善美」とは、倫理・道徳的な価値観が重要となるこれからの時代に必須な価値観なのです。
「友情・努力・勝利」の強固な土台の上に、「多様性」の彩りを添えて、「真善美」のやすりで磨き上げる。今はその総仕上げの時代に入っているのです。
②プラトンの「イデア論」
1なぜ、プラトンの「イデア論」を取り上げるのか?
プラトンの「イデア論」は、真善美を考えるために、まず第一に本来の人間・社会・国家とはどのようなものかを、理解する上での基礎になる、哲学・科学・宗教の根底にある価値観だと考えられるから。
真善美とは、そのものが「本来あるべき理想の姿」という意味をもつ。
人・社会・国・世界が「本来あるべき理想の姿」を取り戻し、真善美を兼ね備える。そのためには、それらが本当はどのような「仕組み」で成り立っているのかを、理解することが重要です。なぜなら、その仕組みが分かって初めて、それらを良くするためには、どうしたらいいのか? あるいは、どうしたら悪くなってしまうのか? が理解できるからです。
その人・社会・国家が、本来どのようなものなのかについての議論は、古今東西あらゆる分野で、様々にされてきました。現代では科学も発達して、従来までは分からなかった人間に関する重要なことが解明されてきています。その中には、本来宗教やほかの領域で昔から言われていたものの、有効性を示すものも決して少なくはないのです。
それらを踏まえて、プラトンの哲学の大まかな概念は、一番シンプルな形式で、哲学・科学・宗教の垣根を越えて、人・社会・国を理解する基礎になる価値観だと考えられるからです。
2ソクラテスの「徳」
ソクラテスの「徳」とは、目に見える道徳的な行いを生じさせる源であり、人が幸福に生きる為に必要な目に見えない「魂の良さ」を表すもの。また、その魂の良さを保つためにする「魂への配慮」のことでもある。
プラトンの「イデア論」は、師匠であるソクラテスの「徳」の哲学を引き継いで、発展させたものです。
ソクラテスは「心の良さ」の根拠を求めて「徳とは何か」という問いを立てました。
目に見えるもの、例えば、パソコンやボールペンなどはわざわざ「それが本当に存在しているか、否か」を問う必要はないでしょう。見ただけで分かるからです。(カントの「物自体」のような「存在論」はここでは一旦無視します)
でも、「心の良さ」とか「徳」って目に見えませんよね。人の素晴らしい行為や言葉になって、表れることはありますが。でも、人の行為や言葉って、受け手によって、感じ方が違いますよね?同じ人の言動でも、素晴らしいと感じる人もいれば、そうじゃない人もいる。
ですが、ソクラテスはそうじゃなかったんですよ。そうじゃなくて、その「心の良さ」や「徳」が、誰に言っても納得せざる負えないような、普遍的で絶対的な根拠が欲しかったのです。人の行為や言葉を介してではない。「道徳」や「善」のようなものがそれ自体として、目には見えないけど、純粋に存在している。そのことの確証が欲しかったのです。
3「無知の知」
ソクラテスの「無知の知」とは、「徳」「心の良さ」などの眼には見えない、普遍性を持つ概念の根拠を見出す客観的な議論に、人々が参加するために、各人が個人の感覚にとらわれた「主観的な思い込み」に気づくこと。
ソクラテスは、人々がその「普遍的で絶対的な根拠」を見出すためには、とても大きな壁があると感じていました。人々が常日頃からあまりにも、物事を自分の都合のいいように見過ぎている。主観的な思い込みに囚われすぎていると考えていたからです。
そして、その主観的な思い込みの「メガネ」に、人々を気づかせる。 そして自分が見聞してきた物事・世界は、それの本当の姿ではないのかもしれない。この自分の無知に自分で気づくのが、ソクラテスの言う「無知の知」。そうしてから、はじめて人々を客観的議論の場に引き出すことができる。そう考えたのでした。
そしてそのための手段としては「対話」が一番いいと考えました。でも、対話と言っても普通の対話ではありません。相手に深く考えさせて、自分の中にもともとある答えを、探し出そうとする対話です。そういう面ではカウンセラーのカウンセリングに近いかもしれません。あっ、でも「あなたは、本当は何がしたいの?」と訊ねたわけではありません。「徳」や「正義」や「勇気」などの概念についてです。「徳って何ですか?」って聞いたんですよ。道行く人々に。これが有名な「ソクラテスの問答法」です。
ところで、何でソクラテスは「対話」が一番いいと思ったのでしょうか? これにもちゃんと理由があります。それはもともと言葉というものが、文脈や周辺の情報に大きく依存し、その大きな揺らぎの中で存在しているということ。そのため、言葉にはどんな状況においても揺るぎない確定的な「一意性」は存在しない。だからソクラテスは、実際の対話の中で言葉で相手を触発することで、各人の中にある思考の営みの中で理解するしかない、と考えていたからです。
そしてこの言葉の性質は、絶対的な根拠を求めていたソクラテスにとっての一つの限界点でもあったと思います。何の限界点? この私たちが今いる世界の、です。つまり、「確固たるものを見出しがたく常に物事が移り変わっていくこの現世で、いかにして、絶対的な普遍的価値を見出すことができるのか?」 ということです。
4「想起説」の導入
プラトンの「想起説」とは、人の魂は不死であり、生前に見ていたイデア界で、必要な知識はすでに学んでいるため、現世での学習はそれを「思い出す」ことであるという考え方のこと。
ここからがプラトンの出番です。先ほど、「ソクラテスの問答法」で自分の中にもともとある答えを探す出すための対話だと言いました。そうなんです。彼は「人間は答えを最初から自分の中に持っている」と考えていたんです。これはプラトンにも受け継がれました。
プラトンはきっとこう考えたでしょう。「いま目に見えている無常の世には、物事の絶対的な根拠は存在しない。でも、人間はもともと自分の内に答えとなる真理を秘めている。では、それはどこから来た? 人間はそれをどこで手に入れた?」
結論から言うと、プラトンはその根拠を人間の「不死の魂」と「輪廻転生」に求めました。
???……いきなり、ぶっ飛びましたね。文字通り、異次元にすっ飛びました。以下に詳しくご説明します。
要は、プラトンは「人間の魂は不死であり、輪廻転生を繰り返す存在である。人間は現世に生まれる前に、永世を通じて必要なことはすべて学びつくしている。だから自分の内に真理がある」と考えたのです。 人間が「何かを学ぶ」ということは、生前に学んできたことを「思い出す」ということ。
これを、思い出す「想起する」という意味で「想起説」と言います。
そしてこれが、この人・社会・世界に真善美や倫理・道徳が成立するための前提条件なのです。「想起説」「不死の魂」「輪廻転生」はプラトンの「イデア論」を支える屋台骨です。これを抜いては存在しないのです。
でもそもそもの話、「不死の魂」や「輪廻転生」なんて実際にあるのでしょうか? これがなくては成立しない、と言った矢先にその根拠自体の根拠が揺らいでしまっては、意味がありませんね。もともと、このイデア論の「不死の魂」や「輪廻転生」は、当時の古代ギリシャで流行っていた宗教の影響と、言われています。
ですが、これからの時代ではそれも夢物語ではないかもしれないそうです。最新科学、特に量子力学の世界では、「輪廻転生みたいなものも、もしかしたら有り得るんじゃないか」というところまで来ているそうです。
まあ、そうであろうとなかろうと、プラトンのこの人間観はキリスト教や仏教のみならず、あらゆる宗教の教義の中心に据えられています。たぶんプラトンの理論や量子力学関係なしに人類が昔から普遍的に持っていた価値観なのでしょう。
5「イデア」と「善のイデア」
「イデア」とは不死の人間の魂が永世を通して学んできた「知(真実)の内容」のことで、「善のイデア」とはそのイデア「知(真実)の内容」の中で最高位にあって他のイデアを動かすもののこと。
「イデア」とはギリシャ語の動詞「見る」の名詞の受身形「見られるもの」に相当します。永世を通じて「見られた真の姿」っていうニュアンスですかね。
そして各イデア(美のイデアとか勇気のイデアとか)はその最高位に位置する「善のイデア」にあやかるように動くのだとしました。
けっこう、抽象的な概念で分かりづらいですね。プラトンはもともと道徳の存在の根拠が欲しくて「イデア論」を立てたんです。だから「善のイデア」がイデア界の頂点に君臨するのは自然でしょう。
6現実世界における「イデア」
現実世界における「イデア」とは、この現実世界に存在するすべてのものの裏にあってそのものの形・性質を規定している、永遠不変の本質という考え方のこと。
この現世での 「イデア」の役割とは簡単に言うと「設計図」です。あっ、プラモデルや組み立て椅子を買った時に付属している紙っぺらのことではありません。それも「設計図」ですが、イデアの「設計図」は目に見えないより本質的なもののこと。そのものがまさにそのものであるための特徴・形を備えた「鋳型」・「原型」のことです。
以下、具体的にイメージしていただけるように、いくつか例を挙げてご説明します。
プラトン自身は「美のイデア」を例に説明しています。
あらゆるものが美しいのは「美のイデア」を持っているから。だから、人の顔を見て美しいと感じるならば、その人の顔には「美のイデア」があるからである。もし反対に、その人が年を取って美しくなくなったりしたら、それは「美のイデア」を持たなくなったからと考える。「美のイデア」とは美しくあるための美の「原型」であり「設計図」と言えるわけです。けっこう抽象的ですね。
次は、より分かりやすく家具職人の机の制作を例にご説明します。
家具職人が机を制作しようとします。その時に、素材が木でもプラスチックでも石でも、形が四角か丸かそれ以外か、またその大きさの大小を問わず、共通する机のイメージが頭に浮かぶと思います。それはだいたい「四つ足となる棒の上に、少し大きめの板が乗っている」という感じのものではないでしょうか? このイメージが「イデア」なのです。机を作りたいときに、椅子やほかのものを作ってはいけませんよね。なのでこの「机のイデア」は机とそれ以外のものを完全に分ける、現実に存在するすべての机(あらゆる素材・形・大きさのもの)の「原型」であり、本質的な「設計図」と言えるわけなのです。
ちなみにこの「机のイデア」に上記の「美のイデア」が加わると「美しい机」になるのでしょう。白く光る大理石の机か、または花や植物の形を彫ったアールヌーボーの美しい机などと言ったところでしょうか。
たぶん、このままだと「イデア」がただの「想像の産物」と思われると思います。なので、もう一つ今度はより現実的なもので、私たちと切っては切り離せないものを例に説明します。
それは人間や有機体の「DNA」です。DNAは「細胞の設計図」と言われています。その本体は二重らせん構造(縄のはしごを丸めた形)ですね。そのはしごの段の一つ一つについている塩基が、塩基配列で隣り合わせの三つで一つの暗号になっているんです。その暗号が細胞に対して特定のたんぱく質を作る指示を出す役割になっているのですね。それでその細胞はDNAからの指示をもとにその生物の体を作っていくわけです。
そのDNAの塩基配列の中には、人間でいえば人類のすべてに共通なものもあります。その家系で受け継がれていくもの、その個人に特有のものもあります。
実際に、その人がどういう人間に育つかというのは、遺伝子以外にも環境の影響もあるでしょう。なのでDNAですべてが決まるわけではありません。ですが、まず人間のDNAは、その人が「サル」ではなく「人間」であるために必要な生命体要素の核になる部分だと言えるでしょう。人間のDNAは人間の「原型」「設計図」なわけですね。
プラトン自身はあくまでこの「イデア論」を、道徳の存在の根拠を提示するために立てました。なので、それと関係ないもの(机や人間など)のイデアの存在を認めてはいません。
ですが、今ご説明したように、道徳や美や勇気など形が(物理的に)ないもの以外にも「イデア論」が適応できます。
だから「イデア論」はこの世を成り立たせる「核となる法則」と言えるでしょう。
7「イデアの分有」
「イデアの分有」とはイデア界の「イデア」を現実世界における個々のものが分け持っているという見方のこと。
例えば、イデア界に存在する「美のイデア」は、一つしかありません。ですが現実世界に美しいものは多数存在するでしょう。その現実世界の個々の美しいものがその状態で存在しているのはその原型である美のイデアを分有しているためだ。という考え方です。
③真善美の個人的・社会的・政治的意味
1「心身の二元論」
「心身の二元論」とは人間が「魂・精神」と「肉体・身体」という相反する二つの要素で成り立っているとする考え方です。
プラトンは上記のイデア論をもとにして、人間の成り立ちについても言及しています。
まず第一に、人間は「魂(プシュケー)」に位置づけられるとします。このプラトンの「魂(プシュケー)」という概念は人間の知的機能の側面を強調したもの。これはイデア論における「イデア」に相当するものでしょう。DNAとはまた違った意味での「人間のイデア」といった感じですかね。でも人間はそれだけじゃなくて「肉体的な要素」もありますよね。こっちの方は反対に欲求や本能あるいは感情に近いものでしょうか。
プラトンは人間はこの「魂(プシュケー)」と「肉体・身体」の相反する二要素で成り立っているとしました。これを「心身の二元論」と言います。
また彼は、「人間は魂を肉体的な要素から脱却させ、より純化することによって向上を図るべし」と、説いています。
そして、そのためにはその妨げとなる様々な欲望や快楽を退ける。より具体的な方法としては哲学を学ぶこととされています。純粋な「知への希求(ピロソフィアー)」が、徳や倫理を追求し「善く生きる」ことに繋がっていく。そう考えたのでした。
2「魂の三部説」
「魂の三部説」はプラトンの哲学において、魂は「理性(知恵)」「気概(勇気)」「欲望(節制)」の三要素から成り立っている、という考え方です。
上記の「心身の二元論」をさらに分解して詳しく説明したのが「魂の三部説」なのでしょう。
イデアに相当する「理性」、肉体的要素の強い「欲望」、そしてその間に「気概」という新しい概念を入れた三要素。プラトンはこれらが人間の魂の内訳だとしました。
その魂の三つの部分は、それぞれ固有の欲求を持ち、人間の活動を担っていく。全体としては「理性」が主導します。「理性」というのは善悪の判断や何が正しいかの見極め(道徳的なことでもそれ以外でも)で働く部分。「欲望」はそれ自体何の歯止めもなしに欲望を追求します。「気概」はその「欲望」を抑え込み「理性」に従わせる役割を担います。
そして、その三つの部分がそれぞれの役割を果たすために養わなくてはいけない「徳」があるとします。その徳は「理性」には「知性」、「気概」には「勇気」、「欲望」には「節制」がそれぞれ対応します。まあ、「理性」の何が正しいかの判断には知識が要りますし、「気概」が「欲望」を「理性」に従わせるにも度胸が要るでしょう。その「欲望」は限りない欲求を自ら制限する必要がありますね。
ここで重要なのは、ただ単に「欲望」を完全に抑え込んでしまえばいい、わけではないといいうこと。「欲望」は人間の大事な「活動力」の源という見方もできるからです。ですから「理性」の要求に従える範囲内で活性化させておく必要があるのです。
プラトンは、あくまでもこの三つの部分の「調和」が成り立つことが大事だと考えていました。
理屈をこねくり回してるように見えるかもしれません。ですがこの三つの部分は、まさに普段から心の中で感じていることと近いと思います。例えば、明日テストで勉強しないといけないけど「ゲームをしたい」という誘惑がある時。いかにゲームがしたい「欲望」を抑え込み、勉強という「理性」の命令に従わせるかが重要になるでしょう。
3「国家の三部説」
「国家の三部説」とは、国家が「哲学者(統治者)」「軍人・政治家」「生産者(農工商)」の三つの階級に分かれる、という考え方。
上記の「魂の三部説」を国家論に応用したのが「国家の三部説」です。
プラトンは「魂の三部説」の「理性」「気概」「欲望」は、そのまま国家の階級に相当すると考えました。「理性」は国家でいえば「哲学者(統治者)」。イデアを認識した人がなるとされています。これを「哲人王」と言います。これが国家の一番上に立ち、全体を主導します。「欲望」に当たるのは「生産者(農工商)」。そして、「気概」に当たるのは「軍人・政治家」です。彼らは「生産者(農工商)」を「哲学者(統治者)」に従わせる役目がありますね。そして魂と同様、三つの階級が全体として調和しているのがいいとされます。
「哲人王」の思想は、政治と哲学の一体化を表しているのです。
このプラトンの国家論は近代に東西ヨーロッパの国々で国づくりの土台になりました。
例えば、十九世紀のイギリス社会では、倫理学を基礎に置いた国づくりのモデルになりました。その結果、国家指導者の地位にある者には、厳しい禁欲や制限が求められました。それはエリートの他階級への公平無私で献身的な貢献を促すことに成功しました。
また彼は西洋だけではなく日本にも影響を与えています。教育制度では小学校で音楽や体育を習ったり、「文武両道」の価値観もプラトンの「魂の調和」を重んじる思想に由来しています。
それにプラトンの『国家』は今でも、欧米の上位校の必読書になっています。政治を志す学生だけじゃなく、ビジネスリーダーやその他の将来人の上に立つ人たちに学ばれているのです。
4プラトンと民主主義
プラトンは民主主義について、極端な選択を避け穏当な結果に落ち着く「次善の策」として、高く評価していました。
上記の「国家の三部説」や「哲人王」と聞くと、プラトンはかなり理想主義だったように感じられると思います。ですが彼は、現実にそのような体制を実現させるのは、簡単ではないこともよく分かっていました。
まず実際に、多くの人間の間には判断力に必然的な差があります。しかも、優れた能力の持ち主は決して多くはありません。「哲人王」のような一極に権力が集中する体制は、指導者が優秀であれば素晴らしい政治ができるでしょう。ですがそうでなかった場合、損害が非常に大きい。彼はそう考えました。
それに比べ、多数意見は最善を選びもしませんが最悪を選ぶこともありません。
民主主義とはいわば、権力が細分化されて多数の人たちに分散される。なので、為政者は良くも悪くも大きな力をふるうことができないのです。常に極端を排し穏当な選択に落ち着く。哲人王の政治に次ぐ、「次善の策」として、プラトンは高く評価していたのです。
プラトンの哲学は理想を唱えたものでした。ですが同時に現実を見捨ててもいなかったのです。
今の時代は型破りなことがかっこいいとされる風潮があります。枠組みは一度でも外れてみないとどういう形になっているのか分かない。でも一流の人ってプラトンだけに限らず、現実や自分が育った文化圏の常識を軽くは見てない気がします。アインシュタインとかもそうですが、彼らが唱えるものは一見かなり常識外れです。ですが全く現実や常識を踏まえないものではない。むしろそれを踏まえた先に見えてくる「もう一つの現実の姿」な気がします。彼らは「型破り」ではあっても「的外れ」ではなかったんですね。
④プラトン哲学の真善美
ここでは、プラトン哲学の「魂・国家の三部説」を真善美に当てはめて説明します。
一般的にプラトン哲学の中で「美」というと「恋とエーロス」の内容になるのですが、ここではそれは扱いません。
1プラトン哲学と「真」
プラトン哲学における「魂・国家の三部説」で「理性・哲学者」を真善美の「真」に対応させた考え方。
一見は突飛なユートピア思想に見える、プラトンの「魂・国家の三部説」。何かのこじつけに見える。でも真善美の社会を実現させるための、重要なヒントを含んでいるようにも思えます。
まず真善美の「真」は「真実」の意味。簡単に言えば「正しいか、否か」が問われている。
「魂の三部説」では「理性」に相当。「理性」は感情を抜きにした正しい判断を行う部分でした。そして「国家の三部説」では「哲学者」。「哲学」はそれそのものの本来の価値判断を行う学問でもあります。主に思考力が関係してくる分野のようです。
あと、「真実は残酷」とか言いますよね。これってある意味で、人間が好むと好まざるとに関わらず、最初からそう決まっている。そしてその「決まり」によって人間や社会が動いている。心で感じることもあります。ですが、基本的には客観性が強くて、しかも時と場所を選ばない普遍的なイメージもありますね? 勉強していると、大事なことって意外とどの分野でも似通ってる気がします。
それ以外にも、根拠もないのに漠然と「これは、こうなんじゃないか」って閃くことありませんか? そういう直感のようなものって、案外当たってること多いですよね。直感も自分の言語化できない経験則のようなものから来てる感じがします。なので思考力と合わせて直感力も「真」には大事な能力でしょう。
2プラトン哲学と「善」
プラトン哲学における「魂・国家の三部説」の「気概・軍人と政治家」を真善美の「善」に対応させた考え方。
真善美の「善」は単純に「善悪の善」の意味。簡単に言えば「良いか、悪いか」が問われている。
「魂の三部説」では「気概」に相当。「気概」は「欲望」を抑え込み「理性」に従わせる部分でした。「国家の三部説」では「軍人・政治家」。軍人は敵が攻めてきたら国を守る役割ですね。でも政治家は、この文脈に沿って言えば、法律を制定してそれを国民に守らせる役割でしょう。ではプラトンの「国家の三部説」に言い換えます。そうすると、「政治家」はその下層の「生産者」を、上層の「哲学者」の意向に、従わせる役割があると言えるでしょう。
どれにも対抗する存在があって、それに立ち向かわなければならない立場。断固たる意志と勇ましい心意気が必要になってきますね。
あと「善と悪」というと、一般的には道徳や倫理が問われる場面で使われる気がします。主に心の内側の在り方を問う概念ですね。上の「真」と比べるとより主観的な側面が強くなる感じがします。人が意識して人間や社会を良くしていこうとする気持ち。その人の「良心」の程度や「正義感」にも左右されるでしょう。主に感情とあと思考力も少し関わってくる分野な気がします。
なんとなく、強い方が良く、弱い方が悪いというイメージがあります。「悪とは何か?弱さから生じるすべてのものだ」これはニーチェの名言です。じゃあ、これの逆は「善とは強さから生じるすべてのもの」ということになる。まあ、基本はこれでいいと思います。
でも「善悪」の問題ってそんなに単純じゃないですよね?
例えば「正義」という言葉。「何が正義かは、人によって違う」って言いますよね。結局、善悪関係なしに、ただ自分自身がどちらの味方につくか。あるいは好きか嫌いか。都合がいいか悪いか。現実にはそれで決まることの方が多い気はします。
3プラトン哲学と「美」
プラトン哲学における「魂・国家の三部説」の「欲望・生産者」を真善美の「美」に対応させた考え方。
真善美の「美」は「美醜の美」のこと。「美しいか、否か」が問われている。
真善美の中で唯一、物体として目に見えます。
「魂の三部説」では「欲望」に相当。「欲望」は、それ自体では何の歯止めもなしに、欲望を追求する部分でした。「国家の三部説」では「生産者」。簡単に言えば「農工商」のことです。人々の衣食住や生活に欠かせない物資やインフラを生産しています。
「欲望」は際限なしに欲望を追求しました。なので、それだけだと魂の三部分での全体の調和が成り立たなくなってしまいます。ですから「活動力」で使う分だけ残し、あとは品性や健全な生活が脅かされないよう、「節制」という徳で抑える必要がありました。
これと同じように、「生産者」もうまく働くためには、自重しないといけませんね。「何を、どのように、どれだけ作るのか」をです。市場にはニーズがありますから、それに応えないといけません。際限なしに、自分たちが、作りたいものを、作りたいだけ作るのでは(特に社会の基盤を支える産業なら)間に合わなくなるでしょう。
実は、美にも「限定」「制約」の要素が必要だ、という考え方もあるんです。
例えば象の絵を描くとき。必ず鼻を長く描く必要がありますね。体は何色でもいいし、耳の形も少し変わっていてもいい。だけど、鼻を短く描いてしまったら象ではなくなってしまいます。「長い鼻」は象を他の動物から分ける特徴なんです。だから画家が象を描くときは、「長い鼻」を描くという「限定」「制約」を受けるのです。重要な部分を抽出するということです。
芸術に重要な調和やリズムもこの考え方が大事なのです。
「調和」とは別のカテゴリーにある複数のものを違和感なく一つにまとめることです。そのためには、複数の種類のものがそれぞれの一番重要な特徴を備えている必要があるんです。カテゴリー同士が離れていれば離れているほど、それらの本質となるものを押さえる。そうしないと上手くまとまらなくなるのです。
美は調和していると快感を感じますね。感情が動くかどうかも重要なポイントな気がします。また「真」や「善」と比べると「五感」などの感覚的なものも大事になってくると思います。一番身近な存在ですね。
⑤真善美を実現するためにまず大事なこと
これまでの章では、真善美を考えるために重要なプラトン哲学の主要な理論を、大まかに説明しました。 この章では、真善美をこの社会に実現するために、日常生活で心に留めておきたい価値観について、紹介します。それの取り掛かりには、世界救世教の教祖である岡田茂吉の真善美。もう一つは、数学者の岡潔の道義教育。一般的にはあまり馴染みがない二人です。ですが、この二人の言説は私が見てきた中でも直感的に理解しやすいと思ったのでここで取り上げようと思います。
1岡田茂吉の真
岡田茂吉の真善美は、自然との調和や人間本来の美意識を大事にし、日々の生活を豊かにしていくための考え方である。その真は、大自然のそのままの姿のことを言い、真善美を実現・実践してく上で一番基本になる価値観である。
岡田茂吉は「真理」についてこう述べています。
真理とは何ぞやというと、勿論自然そのままの姿をいうのである
引用:『宗教下』
具体的な真理の例としては次のようなことが挙げられています。それは、太陽が東から西に沈み、人間が空気を吸って、食べ物を食べて、排せつをして生きている。というわざわざ大げさに言うまでもない、ごく普通の当たり前のこと。
そう。当たり前のことなんです。当たり前で一番簡単で分かりやすいもの。難解なものほど真理から遠ざかっている、とも一緒に述べております。
真理自体は非常にシンプルです。ただ、「どれが真理か」の見極めと、「なぜそれが真理なのか」の理由が分かるまでは、かなり難解な道のりを辿る必要があるように思います。
2岡田茂吉の善
岡田茂吉の善は、人々がこの世界を幸福や平和に導くきっかけになる心の持ちようのことであるとしている。
岡田茂吉は善について次のように述べています。
悲劇も喜劇も、不幸も幸福も、戦争も平和も、その動機は善か悪かである
引用:『宗教下』
これもすごくシンプルな考え方ですね。ヒーローものの「勧善懲悪」の世界に通じます。
でも人生経験がそれなりにあるなら「現実はそこまで単純じゃない」って思う人もいると思います。私もそう思っていました。
だって、誰だって最初から「不幸になりたい」て思って生きてる人いないじゃないですか? 普通に皆幸せになりたいと思って、自分なりに考えて「これは良い」と思ったものを選んで生きている。でもその結果、悲劇や不幸や戦争に陥ってしまうことだってよくあるわけで。これ、「なんでかな?」って思っていたんです。そしたら、同氏の気になる言葉を見つけたんです。それが、
善人とは”見えざるものを信ずる”人であり、悪人とは”見えざるものは信ぜざる”人である
引用:『宗教下』
ここでいう「見えざるもの」というのは、「目に見えないもの」のこと。人の心だったり、明言はされていないそのもののバックグラウンドとか、言葉にはできないけど、確かに感じるある種の感覚など。または幽霊や悪魔や神とかもあるかもしれません。
改めて見ると、影や形はなくても、この世界に大きな影響を与えている存在があるように思えます。 見えないものを、信じるか信じないか。結局、それで自分でも気づかないうちに選択するものが違ってくるのかもしれません。
3岡田茂吉の美
岡田茂吉の美は、人間の感性を磨くことで品性や平和愛好思想を育てるものであるとしている。
最後は「美」について。 岡田氏は『芸術』で次のように述べています。
人間の情操を高め、生活を豊かにし、人生を楽しく意義あらしむるものは、実に芸術の使命であろう
引用:『芸術』
昔は私、芸術ってあんまり好きじゃなかったんですよ。なんかの余興や金持ちの道楽みたいなイメージで。存在意義が分からなかったんです。でも美が人間の情操や品性を高めたりする。あるいは心身が辛いとき心の支えになってくれる。ことを知ったり経験したりするうちに、人間の社会にとっての美の重要性を感じるようになりました。
他のところで同氏は、人類の求める理想世界は「芸術の世界」だと言っています。この「芸術の世界」というのは、ちょっと深い意味があるので、また後日取り上げようと思います。
4岡潔の道義教育
岡潔の道義教育とは、『春宵十話』の「私が受けた道義教育」の章に書かれた、自身が受けてきた家庭教育の内容のこと。「道義」とは人として行くべき正しい道という意味。
この章に書かれている中から、特に重要だと思うものを二つご紹介します。
一つ目は「金銭的なものからなるべく遠ざかること」
もちろん、お金は生活に欠かせない、必要不可欠なものです。この現代社会ではお金がないとできることがすごく限られてきます。ですが、それで人間の考えることが金銭面に偏り過ぎると、人間の品性や感性に悪影響が出てくるでしょう。
数学者の岡潔は別のところで次のようなことも言っています。
世界の知力が低下すると暗黒時代になる。暗黒時代になると、物のほんとうのよさがわからなくなる。真善美を問題にしようとしてもできないから、すぐ実社会の結びつけて考える。それしかできないから、それをするようになる。それが功利主義だと思います
引用:『人間の建設』
知性が下がると、真善美が分からなくなって、実用的にしか考えられなくなって、功利主義になる。じゃあ、逆に真善美を考えるなら、実用面からは一旦離れてみる必要がある。お金を主にしては考えないってことですね。この「一旦」っていうのはミソだと思います。どのみち、真善美を実現するには、その実用面や金銭面も考える必要があるでしょうから。
二つ目は、「人の悲しみが分かる」ということ。
岡潔は「感性・直感を磨くこと」にたびたび言及しており、「人の感情・情緒が理解できるようになれる教育をするべきだ」と提唱しています。
そして人の感情、特に「悲しみ」の感情は一番分かりにくいと言っています。
確かに喜び、怒り、楽しさに比べると「悲しみ」は表情に表れづらいですよね。その人が何も言わなければ、周囲の人にとっては何もなかったように過ぎてしまう。でもその人にとっては、心の奥に強く焼き付いて、情緒の核にもなり、ふとした時にもそれが蘇る、こともあるわけで。ただ言ってくれたとしても、自分に似たような感性や経験や想像力がないと、理解しづらいですよね。
そのためか、岡氏は「道義の根本」は「人の悲しみが分かること」であるとはっきり述べています。
そして、「人が悲しんでいるから、自分も悲しい」の領域。人の共感性がそこまで上がったものが本来の「宗教」だと言っています。
⑥人を幸福にしなければ、自分は幸福になれない
最後に先ほどご紹介した岡田茂吉氏の書籍の中での私が好きな個所をここに引用します。
私は若い頃から人を喜ばせることが好きで、ほとんど道楽のようになっている。私は常にいかにしたらみんなが幸福になるかということを念っている。これについてこういうことがある。私は朝起きるとまず家族のもののご機嫌はどうかということに関心を持つので、一人でもご機嫌が悪いと私も気持ちが悪い。(中略)
こんなわけで、罵詈怒号のような声を聞いたり、愚痴や泣言を聞かされたりすることがなによりも辛い。また一つ事を繰り返し聞かされることもずいぶん辛い。どこまでも平和的、幸福的で執着を嫌う。これが私の本性である。
以上述べたような結果が、私をして幸福者たらしむる原因の一つの要素であるという理由によって、私は”人を幸福にしなければ、自分は幸福になり得ない”と常に言うのである
引用:『宗教下』
ここには「~しなければいけない」という義務的な口調で書かれています。ですが神様というのは「義務」として嫌々やったものはお好きじゃない。でも自分に余裕が出来たときに、いつもより少しだけでも多く他人を思って行う親切や善意は大好きだ。ということも他所で書いていた気がします。「親切」はする方もされる方もいい気分で行いたいものですね。
⑥まとめ:真善美の理論と実践について
この記事では、真善美について、プラトンの「イデア論」を軸にしてご紹介しました。また後半では、真善美を日々の生活や人生の中で実践していくうえで、役に立つ考え方として、岡戸茂吉や岡潔の言葉を少し取り上げてまいりました。
要点を軽くまとめると
倫理や道徳の存在の根拠を主張するため立てた、古代ギリシャの哲学者ソクラテスの「徳」という概念。それを受け継いだプラトンは、その「根拠」を五感で知覚できる感性界を超えて、直感でのみ捉えられるイデア界に求めました。そのうえでさらに、人間の魂は不死であり輪廻転生によって、生まれる前にこのイデア界でイデア(真理)を見てきたため、もともとこの世のすべての疑問に対しての「答え」を内に秘めている、としました。
そこから、人間が「学ぶ」というのは、イデア界で見てきたイデアをもう一度「思い出すこと」だとしました。これを「想起説」と言います。
直感のみで捉えられるイデア界のイデア。そしてこのイデアが、この現実世界を形づくっている、目には見えない「原型」であり「設計図」の役割をしていること。
さらにこの説を発展させた「魂・国家の三部説」で人間と国家の成り立ちを説明。それから、私個人がこの二つの「三部説」をもとにして真善美について少し考察しました。
そして最後にその真善美の実践編として、世界救世教の教祖・岡田茂吉の真善美の概念と、数学者の岡潔の道義教育を紹介させていただきました。
結論として、真善美の社会を実現させるためには、
人間やその集合体からなる社会や国家が、どのような仕組みでできているのか。それが本当に理解できて初めて、人間は大自然に順応して、本来の感性をもとに生きることがいかに重要か。
が大事だと分かるのだと思います。